門倉貴史『統計数字を疑う』

- 作者: 門倉貴史
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2006/10/17
- メディア: 新書
- 購入: 18人 クリック: 269回
- この商品を含むブログ (85件) を見る
「みせかけ」ということは、実態の方は変化していないということだろう。にもかかわらず「みせかけ」が急減しているということは、急減するように交通事故死亡者のカウントの仕方が変わったのでなければならない。著者は、警察庁のカウント対象がが事故後24時間以内死亡者のみであるのに対して、厚労省のカウント対象が「事故発生から死亡までの時間にかかわらず、 一年のうちに交通事故を起こして死亡した人」(p. 6)であること(つまり警察庁カウントより範囲が広いこと)に言及している。
しかし元の問いは警察庁のカウントにおける「急減」にのみ関するものだったのであって、別のカウントとの比較は意味がない。警察庁カウント自体に変化がなければならない。しかし実際には、警察庁のカウント方法には変化はない。さらにいうと、事実としては、どのようにカウントしようと「急減」していることには変わりないのだ(下図)。
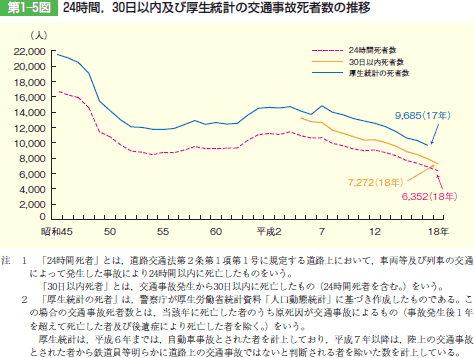
ということは「急減」は全然「みせかけの現象」などではない。というか、著者自身が次のように言ってしまっている。「救急医療の著しい技術進歩によって少しでも延命が可能になれば、最終的には死亡しても、統計上の交通事故死亡者数は大きく減るということだ。」(p. 6)「最終的」ってなんだよ!という話はおいておいたとしても、少なくとも実態としても、救急医療の進歩を一因として、24時間以内に死ぬ人の数が減っているということは著者もわかっているのである(実際には、上図のとおり、その後も含めて死亡者数は減っているのだが)。それをどうして「みせかけ」などと言えるのか理解に苦しむ(それも「統計数字を疑う」という本の一番最初のところで!)。
平均○○というときは、なにが分母かが重要だよ、というのはそのとおりなのだが。無理に「実感とのズレ」の話に持って行こうとして変になっているのが平均初婚年齢の話。
身の回りで結婚時期の遅い人が急増している場合、それが平均初婚年齢に反映されるのはずっと先の話で(しかも一生独身の場合は平均初婚年齢にまったく反映されない)、公式統計に表れる平均初婚年齢と、私たちが肌で感じる平均初婚年齢に大きなズレが生じることになるのだ。(p. 49)
平均初婚年齢というのは、その年の初婚者の平均年齢のことなので、未婚や一生非婚の人は計算に入っていないと。なるほど。問題なのは、「肌で感じる平均初婚年齢」という代物。我々の実感は身の回りの事例に基づくものなわけだが、じゃあ、「肌で感じる平均初婚年齢」のもとになる身の回りの事例とはなにかというと、身の回りで結婚したという話が伝わってきた人や、「結婚しました」報告があった人や、自分が結婚式に招待されて出た人や、テレビとかで結婚しているのをみた人の平均年齢だろう。
さて私は東大の博士課程修了という日本における超高学歴者で、当然まわりもそんなかんじで、したがって平均初婚年齢の実感値がかなり高い方だと思うのだけど、男性30歳というのを聞いても、まあそんなもんかなとしか思わない。そんなもんでしょ?
現在未婚の30代がそのうちたくさん結婚するようになったら、当然統計数値としての平均初婚年齢も上がるけど、身の回りの事例も増えるわけで実感値もそれに伴って上がるんじゃない?
というわけで、平均初婚年齢というのは統計値と実感値の「ズレ」が比較的少ないものだと思うのです。
合計特殊出生率についても、著者はやはり実態とズレているというが、私の実感としては、これについてはそもそも実態なるものを想像することが難しい。
本書にも書いてあるし、報道でもよく言われる「一人の女性が生涯に産む子供数の平均である合計特殊出生率」というのが変な感じなのだ。だって、「今年の合計特殊出生率」とか「今月の合計特殊出生率」とかいうわけだが、明らかに一人の女性の生涯は一年とかひと月ではないのであって、実態として何をイメージしたらいいのかわからないから「ズレている」ということすらできない。
合計特殊出生率でいう「一人の女性の生涯」というのは、現在生きている各年齢層の女性を平均してくっつけて擬似的につくったものなので、なんかちょっと気持ち悪いんだよな・・・(ホッブズ『リヴァイアサン』の表紙のおっさんとか、『占星術殺人事件』のアゾートみたいな感じで。)
第3章「経済効果を疑う」は、シンクタンクの試算への著者の不信感が強すぎて(あるいは読者に不信感を抱かそうとする気持ちがはやって)、著者の批判自体がいいかげんで信用できないものになっている。試算を評価する際に重要な基準について、適切な指摘をしているとは思うのだけど、批判対象のシンクタンクの試算がその基準を満たしているかどうかを検討しないまま、一方的に批判してしまっている。
たとえばクールビズの経済効果の話。
クールビズでカジュアル衣料の売上が伸びる一方で、値段の高い夏用のスーツやネクタイの売上が伸び悩むから、その分のマイナス効果を考えなくてはならない。(p. 127)
そりゃそうだ! でも、批判対象となっている読売新聞の記事を見ると、
試算によると、サラリーマンなどが軽装を一式買いそろえた場合、夏用スーツを一着新調するのに比べて、量販店で二万円、大手百貨店で四万円の支出増となる。(p. 126)
マイナス効果考えてるじゃねーか!
というわけで、その他の例も、新聞記事を参照するだけで、試算の内容には全然触れないまま。
その一方で、「シンクタンクの名前は筆者の判断で伏せてある」という文言が随所に出てきて、あたかも名指しで批判するとその機関がつぶれかねないような、そんな決定的な批判をしているんだぞ、という印象を与えようとする小手先テクニックが見え見えでぞっとしない(←死語。「感心しない」という意味ね。)。
第4章「もう統計にだまされない――統計のクセ、バイアスを理解する」というタイトルにだまされたorz このタイトルだと統計を扱う際の一般的な心構えとかチェック方法の話かと思うじゃないか。
実際は、GDPとかマクロ経済統計の細かい話なのでほとんど飛ばし読み。前章までと議論の精度が全然違うんだもの。著者か編集者か知らないがタイトル付けた人に一本取られた(ほとんど詐欺だけど)。